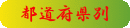今月の土鈴 2025年8月
江戸時代の
人物土鈴
3月からは歴史上の人物の土鈴を時代順にシリーズで取り上げています。
今まで取り上げたのは古代の人物、飛鳥から平安時代、 鎌倉・室町時代、戦国時代(1)、(2)でした。
続いて今月は江戸時代の人物土鈴を御紹介します。
松尾芭蕉

松尾 芭蕉は、江戸時代前期の俳諧師。現在の三重県伊賀市出身。
伊賀の観光土産や旅姿の土鈴が多いです。
和藤内

和藤内は中国における明朝復興運動の英雄、鄭成功をモデルとした『国性爺合戦(こくせんやかっせん)1716年初演』の主人公。
父は亡命した中国人、母は日本人というハーフを作者の近松門左衛門は、和(日本)でも藤(唐=中国)でも内(ない)としゃれて呼んだ。
虎退治でも有名なので、どの土鈴も虎に乗っています。
菅江真澄

菅江 真澄は、江戸時代後期の旅行家、本草学者。本名は白井秀雄、文化年間半ば頃から菅江真澄を名乗った。
天明3年(1783年)郷里を旅立ち、信濃・越後を経て出羽・陸奥・蝦夷地など日本の北辺を旅した。
秋田市に墓があり、秋田とも縁があるのでこの土鈴は秋田で購入。
天草四郎

天草 四郎は、江戸時代初期のキリシタンで、島原の乱における一揆軍の中心人物とされる。 本名は益田四郎時貞。洗礼名は当初は「ジェロニモ」だったが、のちに「フランシスコ」に改める。
水の平焼の切支丹土鈴の中の一つ
大石内蔵助

大石内蔵助(良雄)は、江戸時代前・中期の武士。播磨赤穂藩の筆頭家老。
江戸時代中期に起きた赤穂事件の赤穂浪士四十七士の指導者として知られ、これを題材にした人形浄瑠璃・歌舞伎『仮名手本忠臣蔵』で有名になった。
陣太鼓の土鈴も色々あって、討ち入り時に大石内蔵助が叩いた山鹿流陣太鼓がモデルとされていますが、陣太鼓をたたく場面は講談や芝居による創作でした。
良寛

良寛(1758~1831) 越後出雲崎に生まれ、詩人・歌人・書家としても知られる江戸時代後期の禅僧。
「天上大風」は子供たちが持つうまく上がらない凧に良寛さんが書いた文字で、その後、凧はみるみる空高くあがっていったということです。
新潟県・マリア人形店作
ヘッダーとフッターにも江戸時代に関連した土鈴を並べてみました。ヘッダー左は京都・大石神社の赤穂浪士の陣太鼓、右は大鯨と戦う宮本武蔵、 フッター左は加賀百万石の奴さん、右な太田道灌の笠、「七重八重花は咲けども山吹の実のひとつだになきぞ悲しき」という歌に出てくる山吹の花が付いています。
 昨年同月へ
昨年同月へ 先月へ
先月へ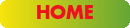
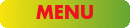
 次月へ
次月へ