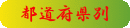今月の土鈴 2025年7月
戦国時代の
人物土鈴 その2
3月からは歴史上の人物の土鈴を時代順にシリーズで取り上げています。
今まで取り上げたのは古代の人物、飛鳥から平安時代、 鎌倉・室町時代、戦国時代(1)でした。
今月は先月に続いて戦国時代の人物土鈴を御紹介します。
武田信玄

先月は三英傑と呼ばれる信長・秀吉・家康でしたが、それに対抗できるのはやはり武田信玄です。
武田信玄のイメージから達磨さんの形もあります。
伊達政宗

続いて伊達政宗の土鈴です。
地元仙台の堤人形の作品も多いです。
加藤清正

左から古博多人形・中ノ子勝美、津屋崎人形、人形陶房美くり鈴「瞠」、博多人形・井上博秀の作品です。
黒田 官兵衛

戦国の三英傑のうち、織田家(羽柴秀吉の重臣として)、豊臣家に重用され、筑前国福岡藩祖となった黒田 官兵衛(孝高・如水)の出陣姿の土鈴です。
兜は、お椀を逆さにしたような形が特徴で、如水の赤合子として恐れられていたと伝えられています。右側の官兵衛が手に持っているものは「采配」というそうです。
海老天たまこ作
真田幸村

真田幸村(信繁)の出陣姿です。
2016年は大河ドラマ「真田丸」が放送されて真田信繁(幸村)もヒーローとして活躍しました。そんな時期に作られた土鈴です。
幸村といえば赤備えの甲冑で鹿角の前立の兜がイメージされます。六文銭の扇も持っていざ出陣、そんな場面を土鈴になりました。
海老天たまこ作
大阪城と真田幸村

真田幸村といえば大坂冬の陣・夏の陣、大阪城を守って大活躍したイメージが強いです。
そこで、真田幸村が城を守るかのように天守の上に乗った大阪城の土鈴です
海老天たまこ作
フランシスコザビエル

戦国時代の人物といえば今まで挙げてきたように武将の土鈴が多いですが、少し変わったところで南蛮人・宣教師のフランシスコザビエルです。
フランシスコ・ザビエルは、イエズス会の創設メンバーの1人でポルトガル王ジョアン3世の依頼でインドのゴアに派遣され、その後1549年に日本に初めてキリスト教を伝えたことで特に有名な人です。
作者は不詳ですが湊焼ではないかと思います。
ヘッダーとフッターには人形陶房美くり鈴「瞠」の戦国武将シリーズの土鈴を並べてみました。ヘッダー左は毛利元就、右は上杉謙信、フッター左は山本勘助、右な浅井長政です。
 昨年同月へ
昨年同月へ 先月へ
先月へ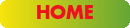
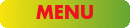
 次月へ
次月へ