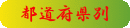今月の土鈴 2025年5月
鎌倉・室町時代の
人物土鈴
3月からは歴史上の人物の土鈴を時代順にシリーズで取り上げています。
今月は鎌倉・室町時代の人物土鈴を御紹介します
義経と弁慶

最初は義経と弁慶、この時代のヒーローです。
鎌倉時代といっても源頼朝の土鈴は少ないですが。義経と弁慶は色々あります。その中の一つ、中尊寺の土鈴です。
柿土鈴でお馴染みの京都・嵯峨野の落柿舎の近くにある「おかもと勇楽」さん作
勧進帳

続いて弁慶さんの土鈴です。
歌舞伎の中でも名作と言われている『勧進帳』の名場面、偽の勧進帳を安宅の関の関守・冨樫の要求通り読み上げた弁慶が、勧進帳に見立てた巻物を右手に、お数珠を左手に持って構えています。
お不動さんに似た形に決めるので、このポーズは「不動の見得」と呼ばれています。
この見得を切っている弁慶さんを土鈴、立ち姿の弁慶さんと達磨さん風にデフォルメした弁慶さんがいます。
これらの土鈴は試作しかしなかったので世の中には1個づつしか存在しません。
海老天たまこ作
北条時宗

博多人形の北条時宗土鈴です。
北条時宗は18歳の若さで鎌倉幕府の第八代執権となり、2度にわたる蒙古襲来という未曽有の難局に果敢に立ち向かったことで知られています。蒙古襲来の重圧に心血を注いだためか、32歳という若さで亡くなりました。
土鈴の姿も若いですね。
雪舟

時代は室町時代に入りました。
雪舟は室町時代に活動した画家・禅僧です。 備中宝福寺(岡山県総社市)での小僧時代、涙で鼠を描いた逸話は有名です。
一休

トンチ話でお馴染みの一休さんの土鈴です。
左上は「第一回マスマス土鈴楽しみマスの会」参加作品、吉備コマさん作の組土鈴です。1合升の中に納まるように作られており、枡を川に見立てて、その上に土鈴の橋を組み立てるとお話のシーンが出来上がります。
左下は「一休さんの虎退治」、京都の洛趣舎・中西庸介さん作です。
中央と右側は京都府京田辺市にある酬恩庵 (一休寺)で授与されていたサッカー少年ととんち博士の土鈴です。
ヘッダーとフッターには色々な弁慶さんの土鈴を並べてみました。ヘッダー右側は三井寺の弁慶の引きずり鐘、左側は同じく弁慶の引きずり鐘で中野和彦さん作、 フッター右側は万兵さん作、左側は作者不詳のカワイイ観光土産です。
 昨年同月へ
昨年同月へ 先月へ
先月へ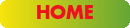
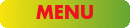
 次月へ
次月へ