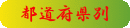今月の土鈴 2025年4月
飛鳥・奈良・平安の
人物土鈴
3月からは歴史上の人物の土鈴を時代順にシリーズで取り上げています。
先月は古代の人物でした。
今月は飛鳥・奈良・平安の人物土鈴を御紹介します
役行者

役行者(本名:役小角(えんの おづぬ、えんのおづの))は7~8世紀に奈良を中心に活動していたと思われる、修験道の開祖とされている人物です。
左側は桝井宗洋さん、右側は箕面焼・松田箕山さんの作品です。
天武・持統天皇

万葉歌人としても知られる天武天皇・持統天皇の土鈴です。
万葉歌を多く土鈴にした桝井宗洋さんの作品です。
聖徳太子

左下の饅頭喰いは子供のころの賢そうな聖徳太子をイメージしています。(海老天たまこ作)
また、昔、お札に描かれた聖徳太子は冠をかぶられていましたが、右側の土鈴は元興寺の聖徳太子像をモデルにしているんで冠は被られていません。 (海老天たまこ原案、カらコロや作)
弘法大師

弘法大師・空海の土鈴です。
空海は中国より真言密教をもたらし、真言宗の開祖となりました。また、能書家としても有名で、嵯峨天皇・橘逸勢と共に三筆のひとりに数えられています。
土鈴は旅姿でしょうか、ふくよかで優しそうな姿です。
余談ですが昨年、奈良国立博物館で開催された空海展は大盛況でした、空海さんは人気がありますね。
紫式部

昨年のNHKの大河ドラマ「光る君へ」の主人公でもあった紫式部です。
左側はほうずき工房(岐阜県高山市)梶野加代子さん作、百人一首の歌人シリーズ土鈴の中の一作です。
右側は江州物産(滋賀県大津市)中野和彦さん作です。
木曽義仲と巴御前

平安時代の終盤、平家政権の末期に登場した木曽義仲と巴御前の土鈴です。
これにつづいて源義経や弁慶の土鈴もあるのですが、それらは次回の鎌倉時代でご紹介します。
ヘッダーとフッターには万葉歌人の土鈴を並べてみました。ヘッダー右側は額田王、左側は柿本人麻呂、フッター右側は防人、左側は大伴旅人を挙げました。 作者は額田王は川崎幸子、他の三体は弟の川崎修一さんです。
 昨年同月へ
昨年同月へ 先月へ
先月へ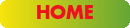
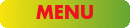
 次月へ
次月へ