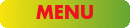(28) 炎の芸術
炎の芸術・美しい音色を探求
金沢大学での学会に参加した昭和30年代の後半、九谷焼の窯元、利岡光仙さんを訪ねて、親しく焼物作りの苦心話をうかがったことがある。 当時、光仙さんのお子さんが明治大学経営学部の学生であり、筆者もまた同学部で教鞭を執っていた関係から、格別の配慮に与ったわけだが、その時、光仙さんは焼き物の生命が火の温度にあることを力説された。 炎といっても、それが還元炎であるか、酸化炎であるかによって、陶芸の素地はもちろん、釉や絵付けの色までが全く違ってしまうものであるし、同じ窯内の温度もすべてが均一ではないだけに、 火の温度に寄せる陶芸家の関心がいかに大変なものであるかという話には、鮮烈な感動を覚えたことだった。
つづいて、昭和39年5月、今日のように観光化する以前の有田に、十三代目酒井田柿右衛門さんの窯を訪ね、当主自ら昔風の作業場や窯場を案内して下さっての説明でも、 陶芸という炎の芸術の神髄は、結局は、窯の作り方と燃料とによる火の温度のかけ方にあるという話を聞き、九谷の場合と同じ感銘を新たにしたことだった。
陶芸の生命が炎にあるという考え方は、土鈴製作の場合も、例外ではない。 ただ、普通の陶芸家と土鈴作家との根底的な相違は、前者が形と色とにその努力の全てを傾注しているのに対して、後者は、それとは別に、ひたすら音色の美しさを求めつづけているところにあった。 したがって、土の性質、窯の構造、燃料の相違などの研究から、例えば、初代の名工柿右衛門が赤絵の製作にその情熱を傾けたように、今日の土鈴作家たちも、音の創作への情熱と四つに組んで、 真摯な精進を重ねているのである。かつて、鈴の音色を良くするために、土を絹漉(きぬごし)にして用いたという話を聞いたことのあるのも、こうした土鈴作家の心意気のあらわれといえるだろう。
また、白魚の土鈴を作ってくれという難題に対して、どのような音を響かせるかと考えた結果、梁筧にかかった白魚の形を製作したという苦心話を、 博多の井上博秀さんからうかがったことがあるが、万象を鈴の形に仕立てようとする旺盛な意欲には頭の下がる思いがする。
この博秀さんを木曾谷への取材旅行に誘って、昨年の夏、島崎藤村の故郷馬篭を訪れた際、土地の古老の案内で、馬頭観音の中に交ざって牛頭観音があるのを見付け出したのが、 この土鈴作家の創作意欲をかきたてるきっかけとなって昭和52年度における同氏の限定作品に、この牛頭観音が選ばれた。すでに藤村の小説「夜明け前」に、馬篭宿での牛方衆の描写が見られたのだから、 牛頭観音を考案した当時の牛方衆たちの切実な願いが、今もなお私たちの心に響いてくるわけで、その切ない響きを土鈴に託して再現したのが、牛頭観音であったといえよう。 それだけに、その型割り式で、作者が心血を注いで作り上げた石膏の型を割る大任を課せられた著者の心境は、まことに複雑であった。
土鈴の手法には、手びねり・型込め・流し込みの3種類があり、土と素肌と土の音とを心底いとしむ甲府の斎藤岳南さんの体験談は、徳間書店の「日本の土鈴」の中に、 ほのぼのとした余韻を留めていて、楽しい。その他、京都三年坂の広田憲一郎さんや、西尾市ハツ面の松田克己さんのように、手作りの土鈴に情熱を燃やす寡作作家など、すぐれた作品を手がけている作者は、数多い。
土鈴は、つまり、音色と形と色彩とのハーモニーによる、炎の芸術であった。
初出 昭和53年(1978年)4月10日(月)
本日の一鈴 牛頭観音 (博多・井上博秀限定)

文章は原則として初出のまま、
注釈や画像は必要に応じて
本Webページの管理者の
責任で追加しています。
 前へ
前へ 次へ
次へ