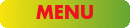(17) 疫病除け
疫病除け 江戸時代初期、枕元に
江戸時代の国学者谷川士清(たにかわ ことすが)の考証随筆「鋸屑譚(おがくずばなし)」(1748)に、「柿本人麿の杜、播磨の明石大倉谷にあり、安産をまもり、火災を避け、祈るに従ひしるしあり。 蓋し、安産は<人生(ひとうまる)>の義に取り、火を防ぐには<火止(ひとまる)>の義に取るなり」の記述があり、ここでは、歌の神として崇められてきた歌聖人麿も、安産・火防せの神にすっかり姿を改めてしまっている。 士清は、さらに筆を進め、人麿社が安産・火防せの神となった言葉のあやに対して、「共に和語の妙、神人の徳、いつわるべからず」と大いに共鳴しているが、これは、つまり、一種の語呂合わせから生じた解釈であった。 したがって、火防せの俚歌として伝えられる「我が家の柿の本まで焼け来てもあかしも聞けばここにひとまる」の呪文も、全く同じ考えからの派生であったことがわかる。
東経135度の日本標準時子午線の通過標識が、その境内にあることによっても名高い明石の人丸神社は、 その社歴も古く、この場所に早く<人丸塚>が存在したことは、「増鏡」の「くめのさら山の巻」にも、その記述が見られる。
この由緒深い人丸神社に、戦後筆者が初めて訪れたのが、昭和41年5月14日であった。 当時、社務所では陶製の人麿像を授与してはいたが、肝心の土鈴は見当たらないままに、神社の前の店に立ち寄ったところ、そのショーウィンドーに、金色燦然と輝く土鈴が飾られていた。 てっきり売り物と思って、早速交渉を始めたところ、店番の老人から、これは売り物ではなく、人丸神社の記念に作って氏子に分けた者との話を聞き、その店に一つしかない土鈴を何とか入手しようと、 薀蓄を傾けて土鈴談義をやってのけた結果、そのずうずうしい情熱に根負けしたのか、ついには、快くその土鈴を無償で譲ってくれた老爺の温情は、忘れることができない。 土鈴との遭遇は、また、人との遭遇でもあったのである。 人丸神社の土鈴は、金塗りで、中程に三本の鉢巻きを持ち、その上に「明石」と「人丸山」の陽刻文字が彫られている。
「誹風柳多留(はいふうやなぎだる)」に、「小児医者赤い紙燭でおくられる」という川柳(明和八(1771)年の川柳)が見えているが、これは疱瘡神祭りの民俗を詠んだものであり、 赤紙の幣束・赤い紙燭・赤飯など、疱瘡神の好む赤色に統一して、病人自身にも赤い着物を着せ、その病苦を軽減しようとする風習であった。しかも悪霊が人間の身体に乗り移ったために起こるのが流行病だという考えは、 日本人の古い霊魂観に基づくものであり、疱瘡神を始めとして、あらゆる疫病神を村境まで送ってゆく行事は日本各地に広く分布している。その疫病を社寺から授与する土鈴によって退散させようとする代表的な存在が、 名古屋市の洲崎神社の神鈴である。これは、黄色・水色・朱色・若草色・紫色の多彩な五鈴を、紙縄で結び、それに「疫病除 洲崎神鈴」と書いたクレープ状の和紙を付けた優雅な出来栄えで、そのいわれは古い。 江戸初期の寛永年間にはじまると伝えられ、病床の子供の枕元に置くと、病気が快癒すると今なお信じられているところに、呪具としての土鈴の観念が見られるのである。
初出 昭和53年(1978年)3月24日(金曜日)
本日の一鈴 疫病除け神鈴 名古屋市 洲崎神社

洲崎の五色鈴 由来
慶長年間市内に疫病が流行した折り、領主が、当社に神鈴を納めて病災解除を祈念したのに始まる。
当社の鈴は、日本の土鈴の代表的なもので、御神木の「いちょう」の実(ぎんなん)をかたどり、五色に彩色され、下げ緒に元結を使っている。
ひなびた土の香り、漂う手作りの味は郷土玩具として高く評価されている。
文章は原則として初出のまま、
注釈や画像は必要に応じて
本Webページの管理者の
責任で追加しています。
 前へ
前へ 次へ
次へ