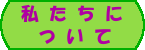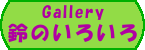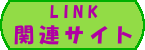栞バックナンバー 第155号 卓話 13
卓話 授与鈴の現況と課題 13ページ目
2.授与鈴の種別と分布状況
(4)授与鈴の変容
授与鈴が変容していくということはこれは当然のことであり多くあるということです。

(イ)祈晴祈雨の馬鈴(貴船神社)→宝船鈴
これも栞にも載っていますが、貴船神社の晴れを祈り雨を祈り願うということから、白黒二種の馬の土鈴を授与していた時が戦後ありました。あそこも水の神様ですから宝船の上で蛇が蜷局を巻いている。 水の神に関わりのある形の鈴でもありました。同じ授与鈴でもずっと授与し続けているうちに、作者も代わってくるでしょうし、色々でな形で変遷していくことがあると思います。


(口)藻刈り船の絵馬→藻刈り船の鈴(安井金比羅宮)
京都の金比羅でも「儲かる」ということで藻刈り船の絵馬がありましたが、一時これを土鈴にした授与鈴がありました。
しかし、今はありません。
「藻刈り船の土鈴」の画像をお持ちの方がおられましたら提供お願いします。

(ハ)うなぎの絵馬→うなぎの絵馬鈴(京都・三嶋神社)
京都「三嶋神社」は子授け・安産にご利益ある別名「うなぎ神社」です。
三嶋神社の神のお使いは、巳蛇(みずち)、すなわち水蛇。棟木のように丸く長いことから牟奈岐(むなぎ)と呼んだ鰻を、水蛇の代表として神使として祀っているそうです。
本来は鰻を書いた絵馬がありましたが、後で土鈴も出されました。以前は鰻も三種の色のものがありましたが今は黒色一色だけになっています。
Copyright © by Kobe Clay Bell Society. All Rights Reserved.