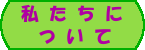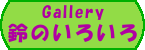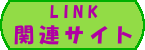栞バックナンバー 第155号 卓話 12
卓話 授与鈴の現況と課題 12ページ目
2.授与鈴の種別と分布状況
(3)伝統的授与鈴と干支鈴との折衷
干支鈴が圧倒的に数が多くなったら、伝統的な授与鈴をどのように折り合いをつけるかという問題が起こってまいります。例として

(イ)干支勾玉鈴(玉造稲荷神社)
玉造稲荷の勾玉を干支の動物が抱えたり乗せているような形になっています。 本来授与していたものは勾玉の鈴でしたが干支のものを上手く折衷してデザインを考えたという形が増えてきました。

勾玉に乗ったのも定番ですね。

(口)破魔矢に神鈴と干支絵馬をつける(熱田神宮)
お参りしたときは本来、「絵馬」を求めます。今の若い方などは「おみくじ」が流行でひかれるようです。絵馬というのは本来は神様に生きた馬を献奉したのが絵馬という形に変わった。 絵馬は神社からもらって帰るのでなく神社に願いを込めて奉納するものです。これが今でも残っているのが、一番華やかなのは受験生が天神様などにお参りに行きます。 必ず絵馬に○○大学合格とか書いて奉納するのです。それが本来の形ですが、いつの間にかひっくり返り、神社から干支の鈴を受けて、それを家に持って帰るという形になった。 元旦詣を見ましても、わりに多くの人は破魔矢をうけてくる。今年も魔を祓って良い年になるように祈って新しい年を迎える縁起物としての破魔矢を受けてくる。
熱田神宮などは大きい破魔矢に絵馬を付けて、その上に「神鈴」を付けて授与している。神主も色々と知恵を絞るようでして、授与の仕方が神社やお寺によって変わって来ているようです。本来、馬を奉ったのが絵馬になった。

例えば、奈良の手向山八幡宮では今でも木製で作った絵馬を授与しています。
そして、同じ形の絵馬を土鈴に作ったものも授与している。というように本来の破魔矢とか絵馬とか授与鈴という関係が。お正月の元朝詣に合わせて色々な形でミックスして考えてくる、 そういうあり方が現在生まれていることを触れてみたいと思って伝統的授与鈴と干支鈴との折衷ということを挙げてみたわけです。