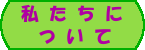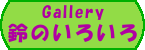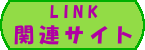栞バックナンバー 第155号 卓話 10
卓話 授与鈴の現況と課題 10ページ目
2.授与鈴の種別と分布状況
(1)伝統的授与鈴
[C群]十二支と重なる関連した神社仏閣に関わるものの類 つづき

◇兎鈴(石上神社)
このウサギさんは石上の神様のお使いだそうです。石上の神様は卯の年、卯の月、卯の日にこの地に着かれたということで卯と関連が深い。
また、方位でいえば卯は東、太陽が昇る方向で古い神社は卯をお使いにしているところが多いということです。

◇猪鈴(愛宕神社)
嵯峨・井浦博氏作。
愛宕神社の神使「猪」の由縁は、神社の創建者である和気清麻呂が猪に助けられた故事に因むとされます。
同じく和気清麻呂を祀る護王神社にもイノシシ土鈴があります。
原文はここまでですがおまけで二つ

◇なでウサギ鈴(大神神社・三輪明神)
日本最古の神社のひとつと言われる奈良県桜井市の「大神神社(三輪明神)」。拝殿に向かって左手、参集殿の入口を入ったところに青銅製の「なで兎」がいます。
その説明書きには『卯は神社にとり、ご神縁の日として崇神朝以来、卯の日にお祭りを毎月奉仕しております。 卯は兎にあてられ、この兎は江戸時代よりの一の鳥居前の大灯籠の火袋を守っていたものであり「なで兎」として伝わっています。』とあります。

◇しぎトラくん(信貴山 朝護孫子寺)
聖徳太子がこの山で毘沙門天王をご感得され、大変にご利益をいただかれましたのが寅の年、寅の日、寅の刻であったといわれています。
そこで信貴山は寅のお寺とも呼ばれます。
しぎとらくんは、信貴山の観光PRキャラクター、いわゆる『ゆるキャラ』です。
美江寺の宝珠鈴も絵馬ということで馬が描かれていました。
干支と関係なくその神社仏閣との関わりを持ったそういった鈴があるということです。従って干支の年になればその神社仏閣は脚光を浴びるというわけです。 授与鈴の分類の方法については、皆さん方も色々なお考えがあると思いますが、私は授与鈴というものを一応A群、B群、C群というような形に分類してみましたが、 また別に他の形でも分類出来ると思います。