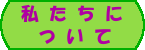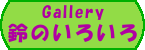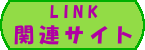栞バックナンバー 第155号 卓話 17
卓話 授与鈴の現況と課題 17ページ目
4.授与鈴の課題 つづき
(3)参詣者(享受者)側の問題点
今年の正倉院展で私が興味を持って見たのは文書関係です。特に、天平宝字年間、昔の戸籍が出て来ていました。 戸籍が実に筆の墨付きなど見事に書かれていました。昔のものがまるで生き生きと、和紙が違うということと、筆で書いているのが時代を超えて残っている。 江戸時代から明治までは新しい戸籍ができるまでは「宗門人別帳」という形でお寺さんが戸籍を預かってきていた。 ですから、お寺と檀家との結びつきは非常に強力なものがあったということになります。 そうなると神社からいえば氏子が居なくなってきた、お寺さんに言わせれば檀家が少なくなってきた。 この二つが神社仏閣にとっては非常に大きな問題になってきている。明治以降の昔は神仏混淆(しんぶつこんこう)でしたが廃仏毀釈で二つに分けてしまった。 その結果がどうなったかといいますと、日本の宗教という考え方では神社は「生」、生まれた命をどのように見守っていくかという面も分担する。 赤ちゃんが生まれてのお宮参り、七五三も、だから神社に行く。お寺さんが引き受けたのは「死」、つまりお葬式であった。お寺さんが引受けだのは人間の終焉、ずばりお葬式なのです、これが主になったことです。 しかも宗教は数多くありますが日本人は大らかで、他国で宗教戦争が起こっていますが、そういう考えは持たない。 日本人は伝統、お祭を重んじ、お祭が好きですが、それは本来の祭ということではない。
だからクリスチャンでないのにクリスマスになれば日本人は世界の人がびっくりするほどクリスマスを祝う、ハロウィンにしても日本ではお盆のようなものですが日本人は上手に取り込んでいる。 そういう面では良い面もあるのですが、宗教という視点は本当は生と死をみつめるというところに宗教がある。 カトリックはマリアの祈りというのは必ず「今も臨終の時も祈り給え」という信仰なのです。 先日、テレビで大神(おおみわ)神社の宮司が話されているのを聞いていますと、外国のキリスト教は信じる宗教なのです。 日本の宗教は感じる宗教なのです。神を“感じる”、そこに行けば神が居る、それを体感するというのが日本の宗教だと説明されておりました。 そういう点で難しい。東日本の震災で年月も過ぎたのですが未だに精神的にも救われない人たちが多く居ます、困るのは神主が例えば、傷ついた人の所にお見舞い、励ましに行きますと歓迎される。 ところがお坊さんが行くとあまり歓迎されない。病院に居られる方のお見舞いに行くとお坊さんは絶対嫌われる。 日本人の考え方というのは仏教のお坊さん、即「死」、お葬式にしか結びついていないのです。だから日本の宗教を考えていく上で、そこら辺をどう考えるか。 そういう問題が出てくるということです。

さて、授与鈴との関係はどうなってくるか。 例えば、伝統が未だに持ち続けられている所、あるいは善光寺などのような大きなお寺、大和にあるお葬式をするようなものではない大きなお寺は観光の上に成り立っているようなお寺が圧倒的に多い。 奈良の大安寺は癌封じを一つの売り物にしていますけれども、癌だけかというとそうではない。 昔は、いわゆる専門があったのです。 受験なら北野天神、長岡天神に行くとか、あるいは少名彦とか久延彦などの知恵の神様に受験生が出かけて行く。お産の神様はどこがいいとか、あそこに行けば守ってくれる。 旅の安全を願う御守を出すのは何処かといえば金比羅と決まっていた。昔は船で行きましたから。 人間が初めて月に到達した年に私は欧州に初めて行きましたが、出かけるその時に金比羅さんの御守の札を貰いました。 飛行機で行くのに船の神様の御守を貰いました。
今は、例えば太宰府天満宮に行くとちゃんと「航空安全御守」があります天神様は雷天神となって太宰府から京都に飛んでいってあの憎らしい藤原時平を襲った(飛梅伝説)ということで、航空御守を太宰府では早くから出されていました。 京都の野宮(ののみや)神社に行きますと「縁結び」のお札をだしています。野宮というのは斎宮に選ばれた方が人間と絶縁として神様の嫁になるいうところだけ取り出して縁結びとしている。 あれは人間とは結婚できないのが本来だから彼処で御守りもらったら絶対良い縁でなく駄目になると。
私の友人が出雲大社に居り、この度は大変な御慶事で、尊い方が御降嫁になるということで、友人は喜んでおります。 まさに、出雲大社は縁結びの神としての本家本元であったわけです。 お詣りをするのは昔は家内安全だけでなく、財政的にも経済的にも豊になりますようにと祈るわけで、そうなると、伏見稲荷が今でも一番であると思います。 稲荷信仰というのは東京では江戸時代以来、屋敷稲荷として商家の屋敷内に稲荷を祀った。現在では日本橋の三越の屋上にも稲荷を祀っています。 考えてみますと近代的なデパートにも何故祀っているのか。そういうことを考えますと神社、仏閣も生きていくために色々考えなくてはいけない。 経済面でも氏子が減り、あるいは檀家も減っていけば経営上も困難なことが起こってくる。 ですから談山神社の宮司に言わせると「内心では、良い鈴を授与鈴に置きたいと思うけれども神社の経営上、高くても1,000円止まり」。 1,000円だと言われると作家の方にしてみれば大変だろうと思います。
「3.授与鈴と作家」に挙げました方々は、昔の良い時代に沢山の素晴らしい授与鈴を製作して納入されていたと思います。