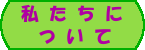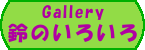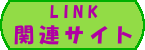栞バックナンバー 第155号 卓話 16
卓話 授与鈴の現況と課題 16ページ目
4.授与鈴の課題
今日は私なりに問題提起をしてみたいと思っていますので、後で皆さん方が考えていただいて今後どうするかということになります。 なかなか大きな問題ですので、ご一緒にお考えいただきたいと思います。
(1)神社仏閣側の問題点
戦後のことからお話してみますと、戦争に負けまして日本人の生活がガラッと変わった。変えさせたのはアメリカです。 それは日本の家族制度です。アメリカは日本に対して一番恐れたのは日本人のあの狂信的な強さというのは何処からきているのかということです。 あの神風特攻隊というのは米軍にとって脅威だったのです。その根底を戦後、アメリカは、一つは「家族制度」、一つは「宗教」にあると。 彼らは日本の宗教をあまり理解していないからキリスト教的な考え方でいた。そこで大きく錠を振るったのは家族制度をぶっ壊すことがアメリカの大きな目的だったのです。 これが見事に成功しているわけです。それが今日に至っているわけです。ですから家族制度が崩壊し核家族化してしまっています。 そうなると最近のニュースで出て来ます「お墓の問題」です。墓はどうするのか核家族化してしまったことです。何処に子供たちが住んでいるか。 昔のように故郷という一つの場所に代々根を下ろして生活をするのではないのです。おまけに核家族で子供の人数が減ってくる。 どんどん広がって行きますと、今生きている老人たちは俺の骨は一体どうすればいいのかということになります。 今は樹木葬とかコインロッカーとかそういう所に骨を何年間保管された後は皆、一ヵ所にまとめて集めてしまう。子や孫に迷惑かけないように将来どうするか。 都営の墓地などはどんどん祀る人がいなくなって一定の年月経てば更地にしてしまう。其処の骨は一ヵ所に集めて葬る。ですから非常に難しい問題です。
(2)土鈴作者側の問題点
現況は大雑把なお話しでしたが、やはり創る作家の立場からのお考えをお聞きしたいので、後は作家の立場から中野和彦さんからお話しを頂ければとお願い致します。
中野和彦さん談

まず、私が神社仏閣を廻るのにあたり、大きな神社、お寺には行きません。というのは御用達会があるのです。例えば三井寺では御用達会の入会に20万円が要ります。 5月には千団子まつりで1週間お手伝いに行かねばなりません。寄付金が年間で三井寺では14、5万の寄付を取られます。大きいところに行くほど御用達会の壁があります。 それと嵐山のある神社では仕入れ担当者の方に個人的なリベートを渡さなければなりません。大きい処には基本的に行きません。逆に小さい所の神社では兼職がものすごく多いのです。 宮司と公務員、学校教員などの職を兼ねている方が多いのです。勤めの後に余計なことはしたくないということです。 大津一宮の建部大社の宮司は5ヵ所の神社を兼ねて居られ大変らしいです。実際に新規開拓に行きましても20件に1件でも開拓できればと思います。 大阪・南河内にある建水分神社の祢宜さんは「神様が中野さんとの出会いを作ってくれました。ずっとインターネットで土鈴作者を探していたのに出会いがなかった。 それが突然に中野さんから電話して頂き、神が出会いを創ってくれた。」(※)というところもありますので、止められません。 年なりに開拓していますので、また、そういう情報がありましたら皆さん宜しくお願い致します。
(神社側にも課題が・・・今は兼職が多い、派遣会社、世襲制)

(※)この出会いにより建水分神社御創祀2100年祭を記念して復元授与鈴「わら人形土鈴」が実現しました。